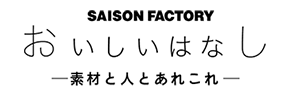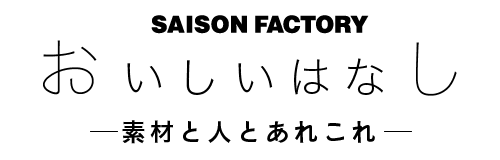団子の木
山形県のあるある?小正月に現れる「団子の木」


先日、とある道の駅に寄ったところ、とても懐かしいものを見つけました!皆さん、色とりどりのお餅や飾りがついた「団子の木」をご存知ですか?
実際に団子が実る木ではなく、山形県では小正月に自宅の居間などに飾るものです。
詳しくは後ほど説明しますが、今回は山形県の文化「団子の木」について、ちょっとローカルなおはなしです。
伝統文化「団子の木」の由来



こちらが団子の木です!我が家には飾っていないので、セゾンファクトリーのスタッフが写真を提供してくれました♪
枝の先についているのが団子、さらにふなせんべいと呼ばれる最中の皮で作った大黒様や恵比寿様、千両箱、宝船、打ち出の小槌、鯛、俵、大判・小判などの飾りを木に下げています。どんな飾りを下げるのかは、各家庭で異なるようです。

山形県の伝統文化である「団子の木」は、小正月(1月15日)に「豊作」や「無病息災」「一家繁栄」などの願いを込めて飾ります。
団子の木に使用するのはミズキの木。水辺に生え水を吸い上げることから「火事にならないように」、ミズキの芽が上向きに生えるため「運が上昇するように」、ミズキの木が早く育つことから「子供が早く育つように」などの願いも込められているんだそう。


調べているうちに、幼い頃きれいな団子の木を眺めていることが大好きだったことを思い出しました。
色とりどりのふなせんべいがとてもおいしそうに見えたので、祖母に食べてみたいとお願いして食べさせてもらったことがあります。ちなみに、味はほぼ無味です(笑)
ただ、下げただんごを焼いたり、ふなせんべいにあんこを詰めて食べることもあるようですよ。
団子の木はいつまで飾る?


団子の木は1月15日の小正月から1月20日の二十日正月(はつかしょうがつ)※まで飾るそうで、1月20日は「だんご下げの日」や「だんごおろしの日」とも呼ばれるそうですよ。
※お正月にお迎えした年神様がお帰りになる日。地域によって異なるが、この日にはお正月の飾り物などを全て片付け終え、締めくくる日とされている。


最近は団子の木を飾る家も少なくなっていますが、道の駅や地域の資料館などではこの時期展示していることもあるかもしれませんね。Instagramでも#団子の木(だんごの木)と調べるといくつか写真が出てくるのでぜひ色んなご家庭の団子の木を見つけてみてくださいね♪